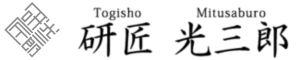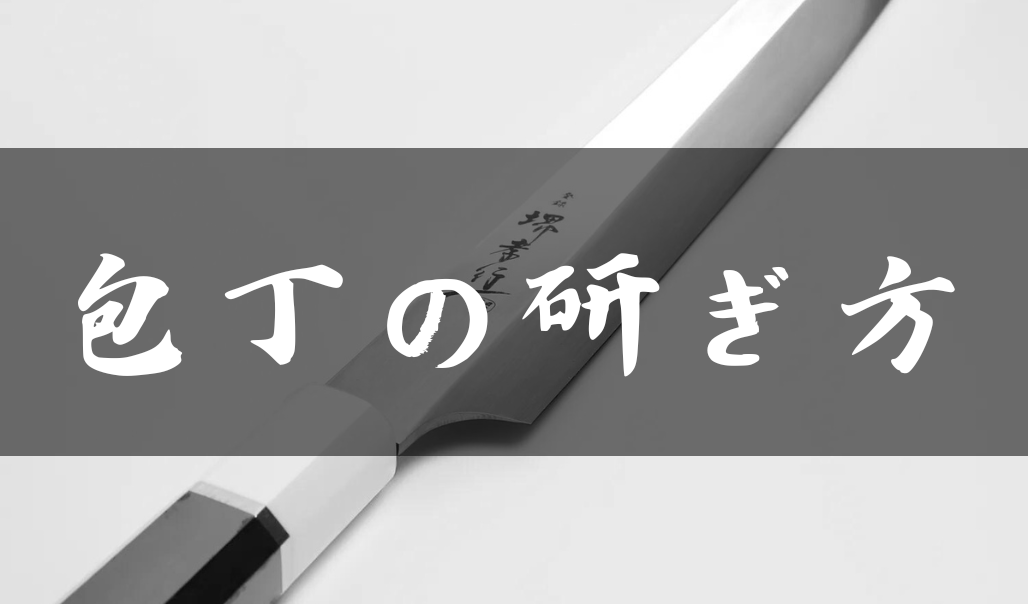皆さんは包丁を研ぐ時、仕上げ砥石を使いますか?
仕上げ砥石とは粒度(#1000)以上の砥石で、おおむね#1500〜#8000以上の砥石が販売されています。
仕上げ砥石は必ずしも使わなくて良いものです。例えば、中砥石の#1000だけで済ましているけど、よく切れる。とか満足していると言う人も大勢おられます。また、あまり鋭い刃を付けると欠けやすいし、危ない!ーと言う人もおられます。
しかしながら、仕上げ砥石のを使えば、包丁の切れ味は格段に上がります。本来、食材を切るために使うのに、わざと切れない包丁を使うのは、かなりもったいないと思います。
何番の仕上げ砥石を使うのかはお好みです。番手が大きくなるほど繊細な刃が望めます。
では、仕上げ砥石はどの様に使うのかをご存知でしょうか?
下記の説明は荒砥石、中砥石で既に刃が付いた状態で仕上げ砥石を使うと言う前提でお話しします。いきなり仕上砥石だけではいくら努力しても刃はつきません。
1、仕上げ砥石は
目が細かいので、長時間水につけなくてOK です。
水をかけながら使うと良いです。
2、基本は刃先の部分を力を入れずに研ぐ!
 研磨と言いますが、研は荒砥石、中砥石で研ぐことを言い、磨は軽く砥石に押し当て研ぐと言うより、みがく!と言う感じです。
研磨と言いますが、研は荒砥石、中砥石で研ぐことを言い、磨は軽く砥石に押し当て研ぐと言うより、みがく!と言う感じです。
注意:この時に力を入れると砥石の表面が黒くなります。これは包丁を研いだ粒子が砥石の目に詰まり、黒くなるのです。こうなると、黒い部分は研磨できません。
 その時は、荒砥石で砥石の表面を前後にこすり研ぎ、黒くなったところ削り取って下さい。荒砥石で仕上げ砥石の表面を平にする要領です。黒い部分は研磨力が落ちます。
その時は、荒砥石で砥石の表面を前後にこすり研ぎ、黒くなったところ削り取って下さい。荒砥石で仕上げ砥石の表面を平にする要領です。黒い部分は研磨力が落ちます。
また、魚をさばいた包丁を洗わず、そのまま砥石で研ぐと包丁についている魚の油が砥石についてしまうこともあります。そうすると砥石表面に黒く油がついてしまいます。この場合も荒砥石で黒い部分は削り取って下さい。
3、最後は軽くなでる様に研ぐ。
仕上げ砥石で包丁を研いでいる時、ついつい力が入ってしまい、表面が黒くなってしまいます。力を入れずに研ぐ、と言うのがなかなか難しいのです。
その時も途中で荒砥石を使って仕上げ砥石の表面を平にする(黒くなった部分をとる)とよいのですが、その時は名倉砥石も有効です。
 名倉砥石は#1000程度の小さい砥石で、仕上げ砥石を買った時に付属している場合があります。別途に購入もできます。名倉砥石で仕上げ砥石の表面をこすることで、砥粒(研ぎ汁)を出し、素早く研磨する事ができます。
名倉砥石は#1000程度の小さい砥石で、仕上げ砥石を買った時に付属している場合があります。別途に購入もできます。名倉砥石で仕上げ砥石の表面をこすることで、砥粒(研ぎ汁)を出し、素早く研磨する事ができます。
#3000以上の砥石で研ぐと和包丁の刃金の部分が鏡の様に光ってきます。この様な光が出ればOKです。
4、最終仕上げは新聞で!
これまで仕上げ砥石を使ってきましたが、最終的に砥石で研ぎあげるだけですと、目に見えない微細な研ぎカエリがあります。
新聞砥:こう言った時はテーブルに新聞を置き、包丁の刃先を新聞紙に軽く押し当て、手首をきかせ、左右に払うように動かします。これにより、微細なカエリが取れ、完璧な刃が付きます。この時、新聞紙は何部かを重ね、弾力を持たせた方が包丁の刃を傷める心配がないのでおすすめです。
 革砥:この新聞紙に代わるものが革砥石です。最近では革砥石が販売されています。革砥石は台の上に砥石の上に革が貼ってあり、これに刃を押し当てる事で微細カエリを取る事ができます。この場合は包丁を前後には動かせんので、上なら上、したなら下と言う具合に、1方向にこすり当て、カエリを取る!と言う具合です。
革砥:この新聞紙に代わるものが革砥石です。最近では革砥石が販売されています。革砥石は台の上に砥石の上に革が貼ってあり、これに刃を押し当てる事で微細カエリを取る事ができます。この場合は包丁を前後には動かせんので、上なら上、したなら下と言う具合に、1方向にこすり当て、カエリを取る!と言う具合です。